「こいぬのコロは、いない いない……ばあ!」
このセリフを初めて娘に読んだのは、娘がまだ0歳の頃。
寝返りができるようになったばかりで、
絵本を開いてもまだ何が始まるか分かっていなかったはずなのに──
その瞬間、娘はびっくりした顔のあと、くしゃっと笑った。
小さな声で「ふふっ」と笑って、また次のページを待つ。
それが嬉しくて、何度もページをめくった。
そして気づけば、こちらも「ばあ!」と声に出すたびに、顔がゆるんでいた。
【しかけで遊ぶ「いないいないばあ」体験】
『いないいないばああそび』は、しかけをめくると隠れていた顔が出てくる絵本。
ページの構成自体が「いないいない…ばあ!」になっていて、
まるで親が手で顔を隠して“ばあ!”をするのと同じ感覚。
赤ちゃんはこの「いないいないばあ」が本当に大好きで、
この絵本を読み始めると、ページをじっと見つめながら笑いのタイミングを待っている。
我が家では、読み聞かせる側もどんどんノリが良くなっていって、
「いないいな〜い…ばああああ!」と、ちょっと大げさに声を出すのが定番になった。
娘は何度も何度も笑った。
ページをめくるたびに、同じような展開なのに、飽きることがない。
笑いながら、声をあげて、自分でも「ばあ!」と真似しようとしていた。
【“絵”の記憶が、日常の遊びになる】
この絵本の面白いところは、「本がなくても遊べる」ところ。
こいぬのコロや、怪獣のガオーンなど、印象的なキャラクターが多く、
声で聞いた内容を娘が覚えていることがよくあった。
たとえば、スーパーで少し機嫌が悪くなったとき、
「こいぬのコロは〜?」と僕が声をかけると、娘の顔がパッと明るくなる。
「ばあ!」と言うと、ちゃんと“笑顔”が返ってくる。
絵本の内容が、親子の共通言語になる。
それって、すごいことだと思う。
「いないいないばあ」は、遊びであり、安心であり、絆そのもの。
この絵本は、それを形にしてくれる名作だ。
【読者レビューから見える、絵本の力】
実際、この絵本を紹介しているレビューにも、共通する感動が溢れている。
• 「10回以上読んでとせがまれます」(10か月・ご家族)
• 「外でも“ばあ”って返してくれる」(0歳・お母さま)
• 「仕掛けを自分でめくるのが楽しい様子でした」(7か月・ご家族)
娘も同じだった。
仕掛けを自分でめくれるようになってからは、「ばあ!」の主役は娘になった。
僕は横で拍手して、「じょうず〜!」と声をかけるだけ。
読み聞かせから、一緒に遊ぶ時間に変わった。
絵本って、読んで終わりじゃない。
親子のコミュニケーションを広げてくれる、“道具”なんだと思う。
【笑顔のきっかけは、しかけの中にある】
この絵本は、赤ちゃんが最初に出会う1冊として本当におすすめできる。
仕掛けをめくるという「動作」、
声をかけるという「関わり」、
そして「笑い」が生まれるという結果。
この3つが自然に繋がっていて、
とくに育児に慣れていないパパでも、
「笑顔を引き出す」という体験を簡単に得ることができる。
僕にとっても、この絵本は“自信”になった。
娘の笑顔が、自分の声と仕掛けから生まれたという経験が、
「もっと絵本を読もう」「もっと関わろう」という気持ちに変わっていった。

【まとめ:その笑顔、何度でも見たいから】
娘がはじめて笑ったときの顔、
「ばあ!」に合わせて声を出したときの目の輝き。
それは何度見ても、こちらまで幸せになる。
『いないいないばああそび』は、親子の時間を笑顔で包んでくれる。
仕掛けをめくるだけで、心までひらいてくれる。
赤ちゃんが初めて出会うしかけ絵本のひとつとして──
この一冊は、僕のなかではもう“育児の定番”になっている。
これからも、何度でも。
あの“ばあ!”の魔法にかかりたいと思う。
⸻
📚 作品情報
『いないいないばああそび』
作:きむらゆういち
出版社:偕成社
#いないいないばあ #育児絵本 #しかけ絵本
#赤ちゃん絵本 #親子で遊ぶ #絵本の時間
#偕成社 #共感したらシェア
※本記事は実体験をもとに再構成したエッセイであり、プライバシー配慮のため日付や細部を一部ぼかし、理解を助ける目的で時系列や表現を調整しています。
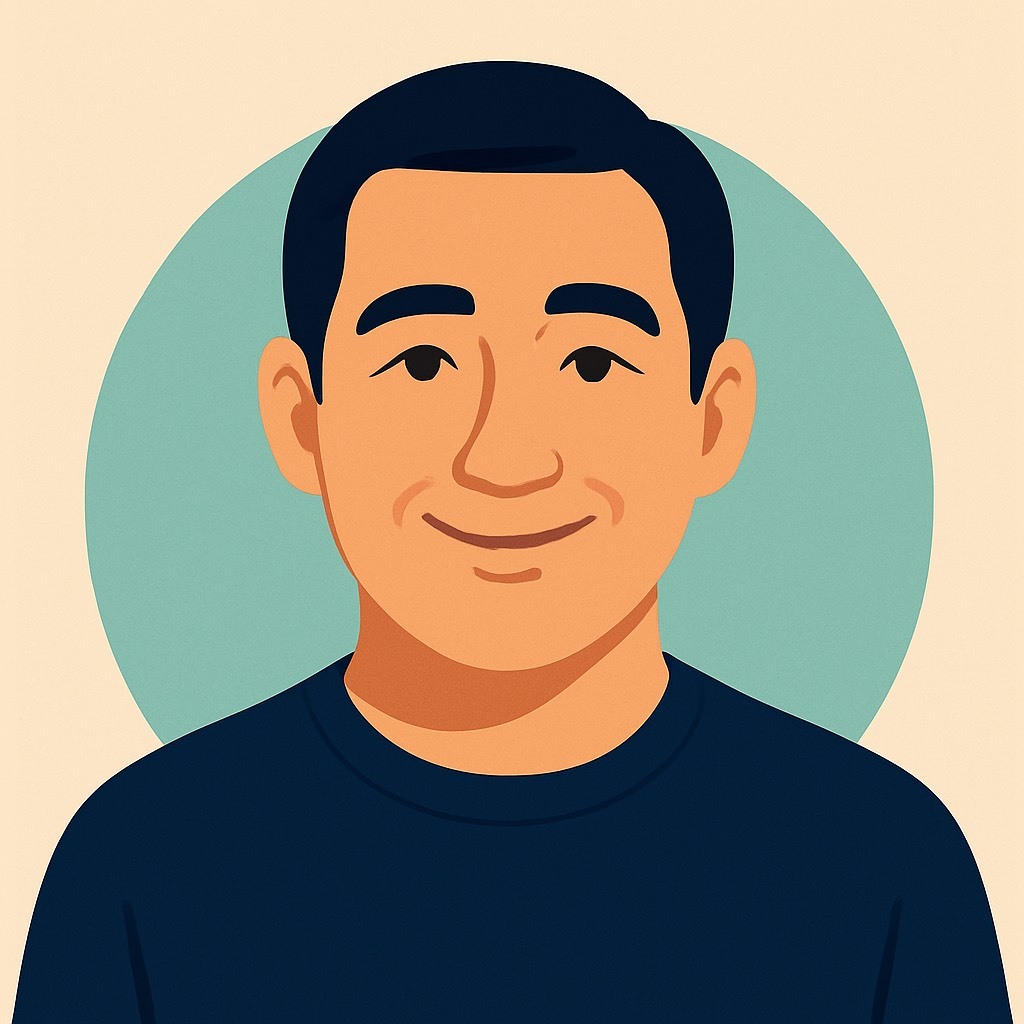
2歳の娘と過ごす日々のなかで、父親としての葛藤や喜びを綴っています。
会社勤務・平凡なサラリーマンだからこそ伝えられる、リアルな「パパの悩み」。
子育てに正解はないけれど、どこかの誰かが「わかる」と思ってくれたら、それだけで嬉しいです。




コメント